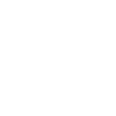The story behind W123
ヤングタイマー
クラシックカーの世界でしばしば「ヤングタイマー」もしくは「ネオクラシック」という括り方/呼び方を耳にすると思う。
これは(「クラシックな自動車」に対して)それこそ「クラシックとは呼べないまでも、モダンとは言えない」自動車のことをざっくり括ったもので、年代的には1980年代から90年代に誕生した名車たちをさす。ファンの中には「このクルマが生まれた時代を知る」人も多く、いわゆるクラシックカーとは一味異なる存在。部品調達や扱いやすさの点ではクラシックカー入門編、現役時代を知る者にとっては「あの頃」が蘇る懐かしいクルマたちである。


自動車の教科書
今回紹介する1976年生まれのW123はヤングタイマーのちょっと手前にいるオールドタイマーのような自動車だ。無謀を承知で四捨五入すれば80年生まれだし、生産も85年まで続いているから、それこそ80年代を生きた自動車とも言えるが、乗ってみるとこれは70年代に開発されたものだと実感する。
自動車は80年代がひとつの転換期となっている。プラットフォームの共有などメーカーのグローバリゼーション化が加速し、社会景気の上向き、人々の嗜好の変化によってクルマが新たな章に突入した、それが80年代だった。一方でオイルショックや安全基準の強化、環境への配慮など、多くの難問にぶつかった70年代は自動車にとって試練の時代。この時代をどう過ごしたか、これによって80年代の自動車づくりの方向性が決定した。
別項でも記した通り、メルセデスベンツはまさにこの試練の時代に現代メルセデスへの道筋を作り上げた。試練を克服したばかりではない。その先を見据えると同時に、「自動車の教科書」を作り上げたのだ。安全で快適、走る、曲がる、止まるという基本性能を徹底的に追求して生み出されたのがW123であり、このミディアムサルーンは、まさに自動車における普遍的なパターンを作り上げたのだった。
ボディバリエーションはセダン、クーペ、ステーションワゴンの3種、他にリムジンもつくられた。

メルセデスの哲学
もしもW123のキャラクターを2つの言葉で示せと問われたなら、誰もが安全性と実用性をあげるのではないだろうか。衝撃を吸収するボディ、高い視認性を備えたライト、死角を排除する広い視界、厚いパッドで覆われた車内、いずれも乗り手を守るために生み出された。実直というより誠実、こちらが相応しいような作りも走り方も、内装、スイッチの配置を含めて、すべて安全性と実用性に基づいて設計された。このふたつこそ自動車づくりにおけるメルセデスの哲学だ。
初めての自動車に乗り込むと、いや乗り込む前からドアの開け方が分からなかったり、ライトが見つからなかったり、どうやったらシートを調整できるのかわからない、誰にもこんな経験があると思う。メルセデスというのはこの手の戸惑いを限りなくゼロに近づかせるメーカー。すべての計器類はシンプルで見やすく、キーシリンダーはじめ操作系は乗り手が”自然に”手を伸ばした位置に存在する。すべての人に門戸を開く姿勢だ。おそらくこの姿勢が世界中で愛されたゆえんだろう。W123は同社でもっとも多く生産されたモデルである。

現代の常識や感覚を当てはめないことがクラシックを味わう秘訣。自分の常識が普遍性を持たないことを知り、世界の広さを感じさせてくれるのが、クラシックの良さとも言える。
例えば走りについては「コツ」を掴む必要がある。300Dターボ・ディーゼルエンジン搭載の300Dとともにポピュラーなモデルが、2.8ℓの直6SOHCガソリンエンジンを搭載する280Eだが、どちらも今の感覚で「ちょこっとぎゅっと踏む」ような運転の仕方はふさわしくない。ひとつひとつのギアをすべて使い切ってゆっくりシフトアップして行くスタイルだから、踏み込む足に力を入れてしっかり加速することが大切だ。こうすることでスピードに乗り、風景、街並みと一体化して行く。重厚感あふれる頼り甲斐のある自動車が乗り手をいざなう。
余裕の風貌
自動車デザインはコストと時間が製作の要となったことで安くスピーディに仕上げることが鍵を握るようになった。加えて社会的存在として自動車が突きつけられた問題、例えば燃費のようなテーマについては技術とデザインがせめぎ合いをはじめて、やがて空力向上にイニシアティブを与えるなど技術先導の時代を迎えた。装飾によってデザインの存在感を見せる、そんな自動車も多い。
ブルーノ・サッコがデザインチーフとして陣頭指揮をとったW123は、技術とデザインのバランスが整っていることも現代にはない魅力となっている。衝撃吸収の目的でボディサイズは拡大化したが、それを美しくまとめ上げた。存在感や車格、風情を与え、「余裕」を生み出した。忙しない暮らしのなかでは、余裕のある実用性こそ理想ではなかろうか。実用性といえば防錆対策が施されたこともあって21世紀を迎えた時点でも4分の3の車両が現役として走っていた、これも付け加えておこう。